|
「何処から来やはったん?うちはお侍は嫌い…けれどあんさんのような人は好き」
「黙って酌しな」
「生意気な御方。…きれいなお顔。きれいな肌。けどその左眼」
「…」
酒を煽る男。
「うちには分かります。何がかなしいのどすか。何がしんどいのどすか。正直に謂うてみておくれやす」
雪が降る。
雪が、降るのである。
深々。
深々。
深々。
夜の底が照らされる。闇の底が白く染められる。
簡単には融けぬ。解けぬ。きづかぬ、
其の儘。おんなは、真赤な唇を微かに吊り上げ、笑みを。
「今晩は寒い。さ、此方へ」
男は、おんなから帯を毟り取る。
毟り取れぬ…
おんなは、男の手を取る。
取りはしない。解って居てやった。
愛しています、とあかい唇
違う
がむしゃらに。
もがいて……
それで何が残った。
雪が降る。
雪が、降るのである。
深々。
深々。
深々。
夜の底が照らされる。闇の底が白く染められる。
簡単には融けぬ。解けぬ。きづかぬ、
其の儘。おんなは、真赤な唇を微かに吊り上げ、笑みを。
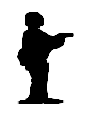
舞うおんな。
平気な顔をして、隻眼の男へはなしかける阿呆が一匹。
「其れにしても、まさか、あの有名な貴方様がこんな遠くまでいらっしゃるとは。江戸を離れた理由は?京まで来て、まさか同胞あつめとは、それだけじゃあないのでございましょう?」
隻眼は顔を上げもしない。三味線片手に、窓辺に腰掛け、気の無い返事。
「何だと思う」
「てっきり、私ァ、天皇の御輿担ぎ上げて、幕府に対抗する気かと…」
「そのつもりだった。だが、気が変わった」
「はぁ…と、云いますと?」
「俺ァ、短気な上に移り気なんだよ。皇尊も結局は幕府と同じ穴の狢…きゃんきゃん吠えるだけで、戦おうという気も無ェのがよく解った」
ゆらりと立ち上がる隻眼。そうして鯉口を切る。隠しもせぬ、その凶悪な音。
「た、高杉様」
「ただ庇護の手を待って護られようとする皇(すめらぎ)…護る価値どころか、存在する価値も無ェ。俺はな、『護る』だの何だのって下らねぇ言葉が一番嫌いなんだ」
冷えきった刀身が、しゅうしゅうと蛇のような声をたてて鞘内を緩慢に滑る。凍りついた男を置き去りにし、ついに隻眼は刀を抜く。
「そして、手前のような、下種も…。疾うに気付いてんだよ、全員出て来い」
男はようやっと悲鳴を上げる。
すると、どうしたことだろうか、ぞろぞろと侍の形をした男たちが、十人余り、部屋に入ってきて、隻眼を取り囲むではないか。
「ほぉ。用意周到で、結構な事だ」
「殺せ!殺せェ!!」
腰を抜かした男が叫ぶ。傭兵たちが一挙にいきり立った。
「懸賞金目当てに、俺の首級狙うか。面白ェ」
刃毀れひとつない、うつくしい刀。舌を這わし、凄然、目冷ややかに恍惚と笑む。
さあ、来いよ。
怖気付いた男達。それでも流石は金で雇われた傭兵、一斉に奇声を発して刀を振りかぶる。
残された唯一の右目がかっと見開かれ、人とは到底思えぬ狂気の笑み。
そして閃光が走った。
舞うおんな。何もしらぬ顔をして、一人陶然と舞う。その白い面に、紅の飛沫が、ぴっと一条付く。
それを合図にしたかのように、一瞬にして鮮血の華が咲き乱れ、どう、と男達は斃れ伏した。
転がる首。腕。真赤な部屋。
「ああああ…………あ…く、くるな……」
唯一無事であった、これら十の死体の雇い主。失禁しそうな顔で、後ずさっている。
「手前も何も出来ず護られるクチか、金の力を借りて。此れ、返すぜ」
返り血をぐっしょり浴びた、凄惨な格好の隻眼は、先程男から手渡されていた大量の金子が入った漆箱の蓋を蹴りとばす。素足で中身を引っ掻き回した。行灯の光に反射して、金色が綺羅綺羅と豪奢に輝き零れ落ちる。
「そ、其れの五倍出す!だから助けてくれぇ!」
「金で手懐けようと?手前には、俺が如何見えているんだ…?」
酷薄な薄い笑み。
一歩。
「あ………あ……」
「人間?…違う。鬼?……それも違う。───獣だろう?」
「来るな…来るなぁぁぁああ!!」
「獣は金じゃあ飼えまいよ。必要なのは金でも、名誉でも、思想でも無い………鎖だ」
尤も、下種には、俺を手懐ける鎖なぞ持ち合わせていないだろうがねぇ?
喉を鳴らし密やかに哂う隻眼に、男は泣き錯乱したまま叫ぶ。
「この人でなしいいい!化け物ォ!ひっひ…あう」
「化け物?人聞きの悪い」
男の首が飛ぶ。噴出した赤い液体。
「化け物は俺じゃない。彼奴だ。クク…ハハハ」
おんなは舞う。一人。陶然と。
雪が降る。
雪が、降るのである。
深々。
深々。
深々。
夜の底が照らされる。闇の底が白く染められる。
簡単には融けぬ。解けぬ。きづかぬ、
其の儘。おんなは、真赤な唇を微かに吊り上げ、笑みを。

おんなは謡う。
隻眼は三味線を弾く。その音に合わせ、女が細い声を張り上げ。
鬢のほつれは 枕のとがよ
それをお前に疑われ
つとめじゃえ 苦界じゃ 許しゃんせ
待てば添われる 身を待ちながら
せめて 世間を狭くする
せかなきゃね 先越す人がある
疑い晴れた この手を離せ
他所で浮気するじゃなし
車もね 来ている 夜も更ける
もしも私が鶯ならば
主の お庭の 梅ノ木で
惚れましたと
エー たった一声聞かせたい 「…おじょうず」
おんなは手を打つ。隻眼は見向きもしない。
そのまま暫く、窓に腰掛けたその格好で雪を眺めていたかと思うと、三味線を爪弾き鳴らす。男が謡う。 三千世界の烏を殺し
主と朝寝がしてみたい 「素敵な都都逸。何方はんが御作りになられたんどす?」
「即興だ」
「如何にも、あんさんらしい。粋。何処のおなごに向けて?」
京おんなは執念深い…呟く淫靡なおんなの唇。
「即興だと云っている。何も考えていなかった」
「嘘。お侍さんは嘘が下手どすなぁ」
男は薄く口元だけで笑い、おんなを組み敷いた。
「違うだろう。御前への唄だ、と俺に云って欲しいんだろう?」
「嘘を吐かれて無邪気に喜ぶほど、うちは零落れとりません」
何を云われても、されても、挑発するような余裕しか見せないおんな。だから男はこのおんなを好いている。 這わす唇。おんなは語る。
京おんなは執念深い…でもあんさんも負けとりませんね。そやけどもうちと違ってあいやがおます。…美しく強靭でどこにやてすきに行ける足。行ってお上げよし。潰すも愛すもあんさん次第。
東へ、お帰りよし。
雪が降る。
雪が、降るのである。
深々。
深々。
深々。
夜の底が照らされる。闇の底が白く染められる。
簡単には融けぬ。解けぬ。きづかぬ、
其の儘。おんなは、真赤な唇を微かに吊り上げ、笑みを。
雪が降る。
雪が降った。
雪が降っているから。
深く。どこまでも深く、闇まで届くから。
その色が、夜の底を照らしていくから。
積もったその色が、融けようとしないから。
解けないから。
網膜に焼け付いた、くれなゐの双眸が、瞬くから。
三
千
世
界
の
烏
を
殺
し
主
と
朝
寝
が
し
て
み
た
い
|

